漢字の感じ
高校生のころだったと思いますが、「世論」が「よろん」でも「せろん」でもいいことになりました。「せろん」は響きがなんとなく安っぽく感じられ、気づいてみれば今でも「よろん」と読んでいます。
 その後、「独擅場」(どくせんじょう)を「どくだんじょう」と誤読して、「独壇場」と書く人が増えたので、認められるようになりました。今でも「独壇場」(どくだんじょう)を国語辞典で引くと、誤読だと書かれています。
その後、「独擅場」(どくせんじょう)を「どくだんじょう」と誤読して、「独壇場」と書く人が増えたので、認められるようになりました。今でも「独壇場」(どくだんじょう)を国語辞典で引くと、誤読だと書かれています。
働き始めた頃、「しんぼう」を「辛棒」と書いたら、大先輩に「辛抱」と直されました。「え」? 辞書を引いてみると、当時私が使っていたS社のには「辛棒・辛抱」の両方が載っています。有名なI社のには「辛抱」だけ。
やりとりを聞いていた別の先輩、「S社のは品がないからI社のを使いなさい。」
なるほど、辛さを抱えるから「辛抱」です。素直に仰せに従いました。
今では辞書はもちろん、パソコンの変換候補にも「辛棒」は出てきません。
割合最近の話ですが、「代替」(だいたい)を「だいがえ」と誤読する人が増えたので、ついに、「だいがえ」でも認められるようになりました。
「昂」・「嵩」・「讃」が常用漢字から外されたので、「激昂」は「激高」に、「嵩じる」は「高じる」、「讃美する」は「賛美する」。「稀」も同じで、「稀有」(けう)は「希有」に、「古稀」は「古希」に。
発音は同じでも、文字から受ける感じが全然違いますよね。
なでしこジャパンの澤穂希さん、なんで「ほまれ」と読めるんだろうと、かなりの間、謎でした。ある時、ふいに気が付きました。稀(まれ)が希になったからです。う~ん、なるほど。
人名はもともと、アルファベット以外、ひらがな、カタカナ、許容漢字の範囲内でどうつけてもいいことになっています。(初の例外が「悪魔」くん。裁判沙汰になりました。覚えておられますか?)しかも読み方は届けませんから、どんな文字をどう読ませてもよいわけです。
サザンの桑田佳祐さん、本来は「よしすけ」で、「けいすけ」とは読めません。けいすけと読ませるのなら「桂祐」か「圭祐」のはず。ですが、彼の影響絶大、佳をけいと読ませる人が急増して、今やパソコンで「けい・・」と打つと、変換候補に佳のつく人名をたくさん挙げてきます。
最近は、音読みと訓読みの一部ずつを組み合わせたりして、読みにくい名前が増えています。キラキラネームです。親がそれだけ思いを込めて命名するのでしょう。
ところが、実は今、戸籍の名前にふりがなを付けることが検討されているのだそうです。許容範囲をどうするかが大問題。
ひとつの案では、漢字から想像できるものはいいとかで、例えば「大空」をスカイ、「光宙」をピカチュウなら〇、「太郎」を じろう、「高」を ひくし は✕となるそうです。カタカナにするか、ひらがなにするかも案がまとまっていないようですが、スカイはともかく、ピカチュウは廃れるかもしれず、子どもが大きくなったら、読み方を変えたいと思わないでしょうか。戸籍訂正の手続きを取るのでしょうが、今なら簡単にミツヒロと読み替えられるのに、面倒ですよね。
文字は生き物。時代に連れ変化していくのが当たり前なのかもしれませんが、時々なんだか寂しいと思います。
と、こぼしたら「夏目漱石や芥川龍之介が文庫本になった自分の作品を読めば、もっとそう思うよ」と言われてしまいました。
ごもっとも。
you

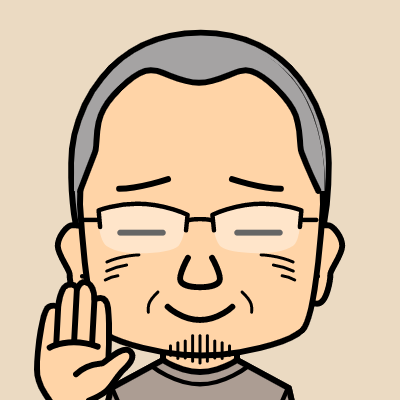

you さん
面白い記事をありがとうございます。
小学校の時の担任が、漢字の読み書きに結構時間をかけてやってくれたおかげで、大人になってとても助かりました。
しかし現代読み方書き方が習ったころとは違う場合でもOKになっており、若い人に「あんた読み方違うわよ」と言えなくなりました。自分が間違っているのか一瞬引いてしまう場面が多いです。
早速のコメント、ありがとうございます。
どの範囲で漢字の使用を認めるか、送りがなをどうするか、決めているのは文科省国語分科会というところらしいです。
勝手に変えないでよ、全然意味が違ってくるじゃない、と怒りたくなることがありますが、そんな時、『おばちゃん』の強い味方になるのは紙製の辞書です。本来の読み方・書き方が何か、はっきり書いてあります。お勧めはやっぱりI社のかな。最新版は2019年発行の第八版です。たびたび買い替えなくても大丈夫だと思います。
私がパソコンに頼るのは送りがな。頻繁に変わるし、規則性もあやしげなので、付き合っていられないからです。
名前のふりがなを検討中なのは法務省法制審議会。あまりセンスがなさそうで、困ったことです。
youさん
この話題、面白い!
我々日本人はもっと真剣に考えるべきだと思ったのは、年寄りの私だけだろうか?
貴殿の最後の一文はまさにその通りと思います。ただし、もう、センスのあるなしの問題ではなさそうに思います。
名前に使う漢字とその読みの関連は、そう読みたい・読ませたいと思う親の思うとおりには行きせん。それほど名前の呼び方にこだわりたい親は、妙な漢字など使わず、全てひらがな・カタカナで表記すれば済むこと。敢えて名前の呼び方にクイズのような漢字をこじつけてそう読まそうなんて思わない方がよくありませんか?
連想ゲームをやっているつもりの親が増えてくるのはなぜか? 審議会のメンバー自体が、そんな同じ部類に入りかけている証拠ではないでしょうか? むしろ、その方が気になります。
「光宙」をなぜピカチュウとして認めるのか? これが認められるなら、「禿」という字は、とっくに「ピカ」でもいいはず。「禿(はげ)」は差別用語として叩かれることがあっても、「ピカ」なら「ピカイチ」というくらいですから、差別など完全に超越しています。
さて、ここでクイズです。私の名前はツルピカ。どのように漢字で書くでしょうか?
ツルピカさん
『ちょっと理屈っぽくて硬すぎるかな』と思いつつ載せた記事を面白いと言っていただけて、ホッとしました。
が、むずかしいクイズを出されて、二晩夢の中でまで考えましたが、回答を思いつきません。
禿というのは常用漢字でも人名漢字でもないので、戸籍に使うことはできません。それに、「かむろ」と読んでおかっぱ頭だったり、江戸時代の遊女おつきの幼女を指すこともあるそうですから、差別用語だとひがまないでください。
クイズ、大真面目なのか、とんちなのか、それすらわからないので苦しいところですが、私はまじめなので、ツルは鶴、都留(山梨県にありますよね)、津留(姓で時々見かけます)、弦(近頃有名です)あたりを考えました。それとも意味からずると滑かな。ピカというのは降参、光しか思いつきません。
youさん
余り趣味のよくないクイズ(でもなかったですね)に大まじめに付き合って頂き、二晩も頭を悩ませてしまったこと、本当に申し訳ありませんでした、お詫びします。そして、有難うございました。
この「ツルピカ」という私のハンドルネームは、昔あった漫画の「ツルピカ禿〇(ハゲマル)」という主人公の名前からのものでした。これは原作がカタカナ表記だったので、もし漢字表記にすると一体どんなキラキラネームになるだろうと考えた末、この主人公の頭がつるっ禿なので、「ツルツル滑らかでピカピカ光っている」ということを連想ゲームのように「滑光」の二文字に込めました。そこまでで、クイズになどせず止めておけばよかったのですが、つい余計なことをしてしまいました。
youさんは非常にまじめにいろいろ考えて頂き、私がつけたツルピカの漢字名に「ほぼ到達」していただけました。流石です。これが審議会で認められるかどうかは分かりませんが。
今後、ひろばにも時々顔を出すかもしれませんが、その時は読めるカタカナ名で。